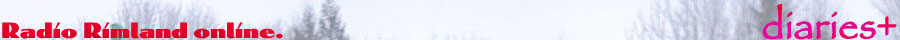
| 記事:2013年4月(普請中) |
←1312
1302→
記事一覧(+検索)
ホーム
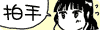
|
洒落にならない話(13.04.02)
 君には表現の工夫や発展というものはないのか、と己にツッコミたくなる昨年と今年の写真。大須・新雀本店の名物みたらし団子。甘味が少なくサッパリした正油味。名古屋に行くとつい食べちゃう。
君には表現の工夫や発展というものはないのか、と己にツッコミたくなる昨年と今年の写真。大須・新雀本店の名物みたらし団子。甘味が少なくサッパリした正油味。名古屋に行くとつい食べちゃう。3/31の名古屋コミティア(おつかれさまでした)で配布したペーパーでも軽くネタにしたのですが、自分も何度か足を運んだことがある名古屋港水族館で「近ごろ緊張感がないマイワシの群れに活を入れるため水槽にホンマグロを投入」という主旨のニュースが新聞社によって配信されました。
ところがコレに当の水族館飼育係を名乗る「そんな意図はない」というコメントが出てきています。
後者のコメントは水族館の公式発表ではなく、ニュースサイトのひとつに匿名で投じられたもので、逆にその信憑性は…?とも思われるのですが、発言の主旨は
・もともとマイワシ水槽にホンマグロは常在し、むしろマグロ飼育のための追加投入である
・マイワシに緊張感が必要とはスタッフは思っておらず、面白おかしく作り話をされ困っている。是正された適切な報道を依頼した
というもの。上記のとおり、発言経路が公式でないことが引っかかる一方、水族館の施設としての目的や方向性として前者ニュースの見世物的なニュアンスにも違和感があったので…うーん、困った話ですね。今後の経緯を見守りたいと思います。
※2017年1月追記:「今後の経緯」どころか、日記にした本人もサッパリ忘れていました。すみません…
もっとも残酷な復讐〜マイケル・バー=ゾウハー『復讐者たち』(13.04.05)
1960年イスラエル政府は、南米に逃走していたナチスドイツ・アウシュビッツ強制収容所の責任者アドルフ・アイヒマンを現地で誘拐・密出国させるという非常手段でイスラエルの法廷に召喚し、死刑を宣告・執行した。ユダヤ系アメリカ人、つまり第二次世界大戦後(というかアウシュビッツ以後)イスラエルではなくアメリカを選んだハンナ・アーレントは1962年『イェルサレムのアイヒマン』を著し、事実上の大量虐殺者であるアイヒマンがただ命令に従った「凡庸な悪人」であることを示して衝撃を与えた(と、いうことに僕の中ではなっている)。同書がもう一つ暴いたのは、ユダヤ人の側にも強制収容に抵抗せず、粛々と自分たちのガス室送りに協力した者さえいたということだ。
イスラエル建国に加わることを選んだマイケル・バー=ゾウハーは六日間戦争などに従軍し、そして1967年『復讐者たち』(ハヤカワ文庫NF)で、アーレントのカウンターになるような「抵抗し、復讐するユダヤ人」もいたことを示した。もちろん著者がアーレントを意識していた、という意味ではない。両者の間にはそれこそ星の数ほどの他の著作・他の考察・他の提示があったろう。あくまで、さほど本を読んでない僕の中での位置づけと承知してください。
むしろアーレントなど間におかず、アイヒマン略取で「イスラエルは復讐をあきらめない」というドスの効いた決意が世界に示された、ゾウハーの著書はそれを補強し裏づける動機で書かれたと見たほうがよいのかも知れない。ナチスの大物小物をイスラエル政府や個人のナチ・ハンターが追い続けることは、そうして捕えた大物小物自身への復讐となることはもちろん、まだ捕らわれていない大物小物にも恐怖を与え、惨めな逃亡の余生を強いる復讐力がある−とは取材した発言者の口を通して著者が繰り返し述べていることでもある。
『復讐者たち』はまず、第二次世界大戦前からユダヤ人は個人によるナチス幹部の暗殺などの抵抗を行なっており、戦中も果敢なレジスタンスがあったことを提示する。そして苦い衝撃を与えるのは終戦直後、連合軍に加わったユダヤ人たちが一定の復讐を為していたという事実だ。
彼らユダヤ人がされたと同じように、ドイツの村のひとつでも女子供を含め殺戮に沈めてやればいい−そんな憤怒は最終的には斥けられる。だがそうした大規模な復讐を避けるかわり、少数の選抜された暗殺部隊が占領下の地域で少なからぬ数のナチス士官を一人一人誘拐・処刑し、またSS(親衛隊員)が収容された施設のパンに毒を塗り千人単位の殺害に成功したという。正直に告白するが、こうした非合法な処刑や暗殺があったと知って「そうあるべきだった」思わずにいることはむずかしかった。そう思ってしまう苦さも含めて、この終戦直後に繰り広げられた「復讐」を知れたことが、同書の収穫のひとつだった。
もうひとつの大きな、そして苦い収穫については後で書く。
最初に記したように『復讐者たち』は1967年の著作であり、おそらくこの分野の先鞭といえる本だろう…と推測される(ほんと勉強不足・決定力不足で申し訳ない)。だから基本を押さえる入門書として最適だろうし、逆に古びた面もある。具体的には、
戦前戦中のレジスタンスや、終戦直後の非合法な報復活動に対し、その後のナチス追及は(アイヒマン誘拐のような超法規的措置はあるものの)基本的に合法的な線で、他国とも協力しながらの地道な調査・告発活動となっていく。そんな中、同書の時点では「まんまと逃げおおせている」アウシュビッツの医師ヨーゼフ・メンゲレ(残酷な人体実験を行ない「死の天使」と呼ばれ、また『ブラジルから来た少年』などフィクションの悪役としても君臨している)は1979年に水死。同書で「追跡者をあざ笑うかのように神出鬼没・ナチス残党の間で隠然たる勢力を保っている」とされたマルチン・ボルマンは現在では1945年の第三帝国崩壊時に既に死亡していたことが確認されている(メンゲレ、ボルマンの末路についてはWikipediaによる)。だとしたら数多くの目撃談は、復讐者たちが追い続けたボルマンとは一体なんだったのか。
だが、同書を読んでもっとも嘆息させられたのは、そうした取り逃がしでもなければ、逆に血の報復の成功でもない。
「私は復讐を信じない」著者のゾウハーは、繰り返し言う。復讐は、誰かがしなければならないことだったかも知れないが、それは決して栄光ではなく、復讐者も殺人の罪意識に苦しむ、やむなき行為だった。彼らが英雄としてではなく、むしろ苦悩とともにそれを引き受けたからこそ敬意をもつという姿勢を、著者は取っている。
「われわれの大部分は復讐者ではない。しかしわれわれは復讐者たちを知っている。
彼らと同一にはなれないが、われわれはこの人たちを尊敬している」
そこまではいい。ため息が出るのは、その著者が「吾々ユダヤ人にとって最高の復讐は、イスラエルの建国だ」と、これも繰り返し言い添えていることだ。
「真の復讐はただひとつ、イスラエルの建国だけである」
「イスラエルこそわれわれの最重要事なのだ。未来が大切なのだ」
この「復讐」とは英語の言い回し「Living well is the best revenge」を踏まえてのことだろう。よく生きることが。『優雅な生活こそ最高の復讐である』という題名の書物もあったと思う。だが、半世紀後の現在イスラエルの「大切な未来」はパレスチナ人たちへの抑圧と弾圧で血まみれなことを。Living well・最高どころか、最悪の復讐になってしまったことを僕たちは知っている。
イスラエルを選び、イスラエルに戦った者として、著者はアラブのイスラム世界が戦前ドイツに協力し、戦後もナチ戦犯の逃亡を幇助したと指摘している(これが先に予告した、大きく苦い収穫)。それは事実であろう。しかし同時に、終戦直後のヨーロッパで復讐にたけるユダヤ人兵士たちが唇を噛んで踏みとどまった民間人の殺戮が、イスラエル建国前夜の暗闘では、ためらいなく行なわれたと僕は別口で読んでいる。
おそらくアラブの側からも同様の報復はありえたろう。
ふたたびアーレントに戻ると、『イェルサレムのアイヒマン』の副題は「悪の凡庸さについて」という。官吏として・小物のまま大量虐殺を実行したアイヒマン、それに逆らえなかったユダヤ人。だが実際に同書を読んで最も心を打たれるのは(個人的には)、そうした「凡庸な悪」に対して、たとえばドイツ人なのに自らの命を賭してユダヤ人を守ったような人物もあった、結局は一人一人が決めるのだという訴えだった。『復讐者たち』は、皮肉なことに逆の方向から、ドイツ人だから・ユダヤ人だから・あるいはアラブ人だからということはないと教えてくれる。人は殺し、報復し、苦しむ。過剰な報復が加害に転化し、他者を苦しめる。そしてさらに報復を受ける。特定の民族だからこうということは、たぶん、ない。
最後につけたしになるけれど、元ナチス軍人たちの逃走にあたり、彼らを助ける元ナチス・元軍人たちのネットワークがあったことも同書では詳細に描かれている。たとえば戦犯として捕まった者の多大な裁判費用を、元軍人会がバックアップしたりするのだ。その潤沢な資金の出処がどこまでクリーンなものか、同書を読んだだけでは判別しがたいし、それが戦争やユダヤ人迫害の被害者に負い目を追うもので「なかった」場合どう思えばいいのか(たとえば平和的な事業で合法的に得た資産でも、そもそもそうして生きて稼ぐことができた可能性自体で、彼らは負い目があると思うべきだろうか?)、僕はまだ決めかねている。
ピートルの街にパンがなかった頃〜デイヴィッド・ベニオフ『卵をめぐる祖父の戦争』(13.04.08)
スチュアート・ダイベックの小説『シカゴ育ち』(白水社)について、その内容の大半は忘れてしまった人でも(などと一般論のように書いているが、すまん要は私だ)冒頭に出てくるパン屋の話は忘れがたく印象に残っているだろう。シカゴのパン屋ではない。若い語り手が知り合った、ロシアから来た老教授が、自分の研究室に故郷オデッサの街の地図を貼っている。地図にはいくつも丸がついており、それは街のおいしいパン屋の場所なのだった。アメリカに居を移した老人が二度と訪れることのない、向こうでも跡形もなく消え去っているかも知れない、おいしいパン屋の−という話。訳者の柴田元幸氏にとっても、これは酷愛のエピソードらしく、氏のエッセイでも「ロシヤ(ロシア)のパン」という言葉だけで立ちのぼる魅力について語られている。だが1942年1月、ドイツ軍の猛攻にひたすら耐え忍ぶレニングラードには、まともなパンすら有りはしなかった。いや、もちろん有る処には有るのだろうが、市内に出回るパンはすでに「人間が食べても毒にならず、材料として加えられるものならなんでも加え」た代物で、噛むとおがくずの味がしたり、噛みきれず歯のほうが折れたりした。爆撃を受けた貯蔵庫の泥は砂糖が溶けこんでいるというので市場に並び、本を閉じる背の糊まで剥がされ煮詰められ「図書館キャンディ」として売られていた。そして「有る処には有る」と書いたけれど、その有る処−秘密警察の大佐の権力をもってしても、卵は見つからなかった…
デイヴィッド・ベニオフ『卵をめぐる祖父の戦争』(田口俊樹訳・ハヤカワポケットミステリ→ハヤカワ文庫)は、実は丸谷才一先生が最晩年のエッセイ集『人魚はア・カペラで歌ふ』(文藝春秋)で「最近読んだ面白かつた本」として取り上げていたもの。不肖の弟子(私淑)が亡き師に出された山積みの宿題を少しでも片づけるつもりで読んだのですが−
もちろん、面白かったです。と同時に、これを推す丸谷先生は本当に先の戦争と、それに伴なう社会の抑圧が大嫌いだったんだなと(ベニオフの話じゃなくて済まないが)しんみりしてしまった。今年の雑誌・文藝春秋の新年号だかに掲載された絶筆の小説の冒頭も、中原中也の詩の一節を題にとり(茶色ひ戦争ありました)終戦後の混乱から幻想世界へ−という話だった。そしてまた、いろんな形であの戦争の不条理を語り続けた丸谷先生だったが、このハヤカワ・ポケミスの一冊のように、その不条理を正面から笑い飛ばす怪作はついに著されなかったな・笑い飛ばすには厭すぎたのだなと、またしんみりしたのだ。
と、言うように『卵をめぐる祖父の戦争』よい意味でまあ、ひどいです。すでに述べたとおり外からの攻撃と内部の困窮・二重に生命の危機にさらされたレニングラード、旧名サンクト・ペテルブルクから「ピートル」と愛称される街で、ひょんなことから秘密警察の大佐でも調達できない1ダースの卵を調達しなければならなくなった少年の、へっぴり腰かつ命がけの冒険というか鼻面引き回されというか。無謀と怯懦・純真と劣情・詩情と下品が紙一重で、しかも柴田元幸氏いうところの「ロシヤのパン」な雰囲気(ただしおがくず入り)。12個の卵のために、なんでここまでという処まで話は滑りに滑り、ついに主人公が
「疲れが増すにつれ、このシナリオのすべてについて疑念が募ってきた。どうしてこんなことが現実でありうる?
わしらはもしかしたら、黒板という空にチョークで描かれた月の下を歩いている魔法をかけられたネズミの一団ではないのか」
と正気を失ないかける場面は不思議な美しさがあって、訳者の田口さんも、この場面は愛着がある由。
冒頭に著者が聞いた祖父の話という設定明かしがあり、上記の引用で分かるとおり、続く本文すべて一人称が「わし」で続くことも、話を寓話か童話めかしている。と言うより一歩間違えば壮大なほら話・いわゆる「人を食った話」なのだけれど、同時に戦時下の貧窮を容赦なくリアルに描く本作では、本当に人肉で蒸しハムを作り闇市に卸している悪人夫婦さえ登場する。それこそ民話の人喰い魔女バーバ・ヤーガのように。
↑…誰が上手いこと言えな・しかも相当にブラックな駄洒落(人を食った話)で申し訳ないが、一部登場人物の際限ない減らず口が感染したと御容赦ください。何を措いても読めとは言わないけれど、読めば損なしの一冊です。丸谷先生もそう書かれていたような。
『卵をめぐる祖父の戦争』映画化もされてるようですが、未見。
スーパー国家に到達する道〜酒井直樹『日本/映像/米国』(13.04.13)
図書館の分類棚だと778「映画」のコーナーにあるのだけれど、映画の本なのだけれど、酒井直樹『日本/映像/米国〜共感の共同体と帝国的国民主義』(青土社)は映画の本ではない。映画の本としても楽しめるけれど『ディア・ハンター』『ビルマの竪琴』『ペパーミント・キャンディ』といった映画を題材に取りながら、イギリスやアメリカ・それにもちろん日本が自国の統合や、植民地主義政策を自己擁護する物語を組み上げてきた(あるいは逆にそうした欺瞞を内部告発したり、あるいは擁護するつもりで馬脚を現して来たりした)メカニズムを読み解くもの。個人的には、光州事件の心の傷を描く韓国映画『ペパーミント・キャンディ』を参照しつつ、グローバリズム推進と国民国家主義が矛盾せず、むしろグローバリズムこそが、自国の植民地化とでも言うべきスーパー国家主義を完成させる、その過程を解き明かす中盤がひとつのクライマックス。
現在のグローバリゼーションが向かっているのは理想的な「国家なき市民社会」ではなく、それとは正反対の「法なき国家」、自国内の人間を国民と非国民に二分し「テロに対する戦争」のように後者に対して警察力を行使する「無法国家」の支配であると著者は分析する。だから(同書が刊行された2007年にはまだ問題になってなかった)TPPに代表されるグローバリズムの脅威に、国民国家の統合・(これも今風に言うなら)絆へのノスタルジーで対抗する戦略は効果がないという著者の主張は検討に値する。また少なくとも、僕などが今まのあたりにして当惑している、グローバル化推進と愛国主義が同じ為政者によって主張される不思議は、不思議ではなくむしろ必然なのだと腑に落ちる。
そして、こうしたグローバル化とスーパー国家性の両輪は、かつて日本がアジアで試み、それをアメリカが引き継いだ植民地主義の、つまり半世紀前からの帰結であり到達なのだと、著者は説く。よくある「過去となったはずの国家主義や権威主義の復活が怖い」ではなく(そうした懸念も十分に有意義だと思いますが)それらは一度も葬られたことがなく、むしろ当時から着々と進展し完成に到ろうとしているのだという視点も新鮮ではないかと。もう少しキレイに要約できるかと思ったのだけれど、ちょっと無骨ですね。気になる人は本書を参照してください。
終盤は映画を離れ、戦後の日本史論争などへの批判的考察。
僕はこの人を勝手に社会学の人と勘違いしていたのだけれど(実際には歴史学)人と人の関わり・他人にどう思われたいか・個人はどう他人を排除するか・それが集団による排除や物語による統合にどうつながるか、といった社会学的な視点が多く見られます。だから歴史や民族や国家といった大テーマを扱いながら、時々それとは別に自分の生活のなかでの逃避や自己欺瞞への反省がふいに巻き起こったり
(たとえば
「彼らに対して開かれてあることは、彼らによって恥をかかせられる者として自分を想定し
恥を感ずる潜在性を基にして彼らと社会関係を作ることである」
「開かれてあることを止めることによって、私は(中略)恥から逃れうると信じることができるようになる」
という文章は、それ自体は歴史上の加害の過去の否認を述べたものなのだけれど、自分自身のパーソナルな振る舞いでの人目に晒されたくないという臆病や、それで世界が狭められてしまう残念などを思い起こさせるでしょ)
逆に「個人レベルでもあるあるソレ」的な視点で国家や民族の自己正当化が類推できたり、そういう効用もある。
映画という、親しみやすい題材を入口にしているので、著者への入門書として好いかも知れません。冒頭に述べたとおり、図書館では「映画」の棚に分類されていたりするので、他の人の映画関連書と一緒に、ちょっと硬派な映画評論として読むのも好いかも。
自メモとしては冨山一郎『暴力の予感』(岩波書店、2002年)、生井英考『総力戦体制からグローバリゼーションへ』(平凡社、2003年)も関連書として宿題の棚に。
| (c)舞村そうじ/RIMLAND |
←1312
1302→
記事一覧(+検索)
ホーム
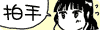
|