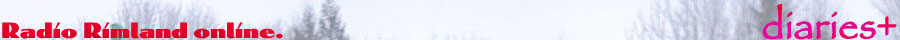
| 記事:2018年12月 |
←1901
1810→
記事一覧(+検索)
ホーム
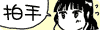
|
言葉を与える〜キム・エラン他『目の眩んだ者たちの国家』(2018.12.10)
2018年11月、同性婚の是非をめぐり台湾で実施された5つの国民投票は、5つ全てで同性婚に反対する勢力が勝利した。アジアで初の同性婚合法化を掲げた蔡英文総統の政策は大きく躓いたと言えるだろう。自分の周囲では家族も友人も、賛成が当然と思われていた…そんな主旨のことを、現地の市民がツイートしているのが目に入った。しかし実際の結果は、その真逆だった。「私の中では聞くまでも無い、当然と思っていた権利や見識が、国民の多数決では尽く否定された。想像以上に世界は広く、壁は厚い」
その悲痛な総括を見て、自分の脳裏に浮かんだのは「泣くな、うつくしい人たちよ、泣くな」というフレーズだった。たしか北村薫『空飛ぶ馬』シリーズの何処かで引用されていた台詞で、元は泉鏡花の作中にあった言葉だったと思う。
吾々は言葉で思考するだけでなく、言葉で認識し、言葉で感じさえする。感情さえ言葉で出来ているとしたら、美しい言葉のストックが多いのは、好いことなのだろう。
『目の眩んだ者たちの国家』。
そんな、たじろぐほどインパクトのある書名を目にしたのは夏、郡山の書店でだった。
2014年、韓国。フェリー「セウォル号」が仁川港と済州島の間で沈没、修学旅行の高校生ほか一般乗客、数百名が水死する事故があった。そもそもスクラップ同然の船体に増設を重ねた老朽船であったこと、乗客には「動かないでください」と指示したまま船長を筆頭に船員が逃げたこと、海上警察などの救援が出ず乗客を見殺しにしたことなど、惨事は複合的な不正と不備によるもので、ひとつの事故を超えた衝撃を、隣国の人たちに与えた。
なぜこんな不正義が看過されてしまった。
これは社会の構造的な失陥の顕れではないのか。
なぜ吾々の社会は、ここまで腐敗してしまったのか。
吾々は、もう落ちるところまで落ちてしまったのではないか。
小説家、詩人、学識者など12人の著者が、それぞれの視点・それぞれの距離感から事故について書いたのが本書だ。
言葉で感じ、言葉で物語り、言葉で思考する人たちが深い悲痛や絶望から析出した言葉・社会への不信や憤り、しかし自分たちもその一員だという自責や悲しみに与えた言葉が、本書には横溢している。それらは国や、もしかしたら時代を超えて、社会の劣化や腐敗に傷つく人々にとって、絶望の蓋をこじ開けるツールとなる言葉の数々だ。
「国家暴力は大衆の虐殺を生む」チョン・ギュチャンは言う。しかしセウォル号の、新自由主義時代のそれは国家の積極的な暴力ではなく、不作為によるもの=「国家がその権力を公益のために行使しない空白状態がもたらした致命的暴力」であると。
「警察力は強化するのに、人命救助にあたる公権力の機能は解体してしまった」「外部からの危険に対抗するために秩序を要求してきた国家が、ほかでもない体制内部で生じる脅威については徹底して無力であるために、災難にさらされる危険な秩序」。
キム・エランは言う。「政府は、必要な措置を次々と命じて民心を安心させる「口」だと自任していたが(中略)国民が本当に望んだのは、権力の「耳」だった」
安保法制、高度プロフェッショナル制度、辺野古の基地建設…採決や工事の強行を繰り返しながら「十分に説明して国民の理解を得られるよう努める」と連呼する、吾が国の政府に対し、誰かが指摘していた。「十分に説明して、理解を得る」とは結局は己の意見を押し通すことであり、国民の声を聞いて政策を修正する意思は皆無なのだと。ふたつの言葉は、海を隔てて響き合っている。
そして社会学者オム・ギホを引用してホン・チョルギは言う。吾々は「互いにぶつぶつ言っているだけ」だと。
それは「自分の私的な経験を、自分だけの苦痛として話すのみで、他人も聞いてくれるような、「公的なイシューを扱う言語」に転換することができない」からだと。そしてそれは「私たちは他人の話を公的な話として聞くことを知らない」「私的なことを公的な話として翻訳する能力がない」ことなのだと。
個人的に興味ぶかかったのは、一年前にハンナ・アーレント『人間の条件』を読んで、恥ずかしながらサッパリ理解できなかった「公共」「政治」といったものが、ホン・チョルギの文章を読んで、ようやく(手袋に手を差し込み、指を動かすように)体得できた気がしたことだ。それを今ここで言うのは恥ずかしいのでしないが
・初読では理解できないことも時間が経つと分かることがある・それは抽象的すぎて分からなかった観念が(この場合はセウォル号事件という)具体例に即することで理解できたのかも知れない、という教訓は記しておいて好いだろう。
不正義に満ちた世界では、その不正を名指すのに言葉が要る。
吾々は言葉で考え、言葉で感じる。ならば、どんな言葉で憤り、どんな言葉で失望すればいいのか。どんな言葉で絶望し、どんな言葉で不屈を誓えばいいのか。本書は、そのヒントになる文例の結晶だ。
公共の、政治の言葉は、(語彙力)などと「クラスタ」に丸投げして済むものではない。
矢島暁子訳・新泉社。
出版社の公式ページはこちら。
| (c)舞村そうじ/RIMLAND |
←1901
1810→
記事一覧(+検索)
ホーム
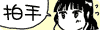
|